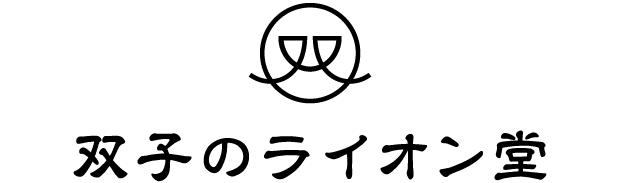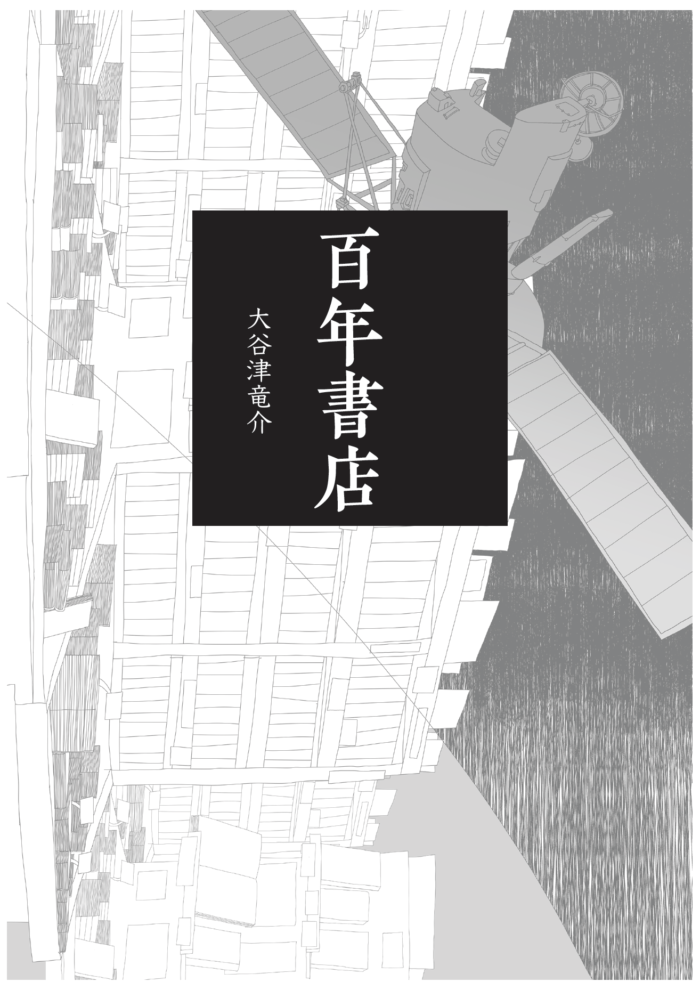
二〇六四年、急進的なアナログ回帰運動の一派〈世界大回帰党〉が事実上世界の権力を掌握した。彼ら自身は、行動を起こしたときには、それがなにか実効的な成果をあげるとはほとんど信じていなかった。
はじめ、アジアの一角でささやかに始まった運動は、わずかな幸運と、掘り起こしたら意外なほど層が厚かった、デジタルを忌み嫌う人々の後押しで瞬く間に、世界を実効支配する力を、その手にしてしまった。
だがすでに二十一世紀も半ばを過ぎていたこの時、デジタル技術を完全に排除して、社会が成り立つはずも無かった。
現実社会とのすり合わせの必要に迫られた〈世界大回帰党〉は、行政やインフラ、経済や学術・文化その他の分野について厳格な規定を設けたうえで、部分的にデジタル技術での管理・運用を許すことにした。これらを管理するAIは、最終的な管理システムという意味で〈限終〉と名付けられた。
だが彼らが世界的に権力を掌握した十年後の二〇七四年、厳格に運用されていたはずのAI〈限終〉は、政権内部の懐疑派によって暴走させられた。しかし最終的に、その暴走は懐疑派にもコントロールできなくなった。そして〈限終〉は自律的に人間とその活動の徹底的な破壊を始め、人類の敵となった。
それから五十年が過ぎた二一二四年、管理AI〈限終〉が開発、生産し操作するドローン類による、人類の虐殺と文明への破壊活動は、一時も休むこと無く、粛々と行われている。
深夜近く、タクラとヤシンは、地下に張り巡らされた秘密通路を〈書店〉に向かって走っていた。地上は、かつて都市だったものの残骸が折り重なり、まともな道は残っていない。
前を行くヤシンが、振り返らずに言う。
「俺たちは今日まで五十年も、懐疑派の連中がやらかしたことの後始末をやってきた。そのために死んだ人間からしたら、俺たちも同じ穴のムジナだ。ふざけるなと言うだろうな。なにしろ、最初の三年で当時の人類の九十八パーセント以上が死んだからな。いま、この地球上で生きてる人間は、二億人もいない」
「その、あんたの言う後始末のために仮体ユニットの強化を繰り返した結果が、その身体か」
警戒しながら小銃型ニードルガンを手に続くタクラが、ヤシンの強化ユニットで盛り上がった背中に声をかける。タクラは敏捷性を重視したボディだ。大小二つのシルエットが、地下通路の仄暗い照明に浮かぶ。
「まあな」
つぶやいたヤシンは、戦闘に特化した身体改造を繰り返していて、生身はほとんど残っていない。それを、かつての世界大回帰党の中核メンバーの生き残りたちは、地上を蹂躙する〈限終〉の版図が広がるのに比例して、贖罪のために人工部分を増やしているかのようだと、囁きあった。
もっともタクラは、外見こそ二十代の青年に見えるが、人間ですらない。レヨンによって隠されていた彼を起動させたのは、ヤシンだ。タクラは、ヤシンのかつての仲間、レヨンから託された、スタンドアローンの完全自律型アンドロイドだ。彼は、人類が〈限終〉から地上を取り戻すための切り札として作られた。
レヨンは、ヤシンと同じ大学の一学年上の女子学生だった。やがて二人とも行き過ぎたデジタル社会の是正を目指す大回帰運動に身を投じ、気がついた時には権力の中枢で、それなりの地位に就いていた。
レヨンは気がつかなかった。その後しばらくして、自分の部下たちの中に、自分たちが作り上げようとしている世界に疑問を持つ懐疑派が現れ、微調整のつもりで〈限終〉に密かに手を加えたことを。
ほどなく、あらゆる分野で原因不明の不具合が頻発しだし、〈限終〉が異常なしを連発するに至って彼女も気づいたが、遅すぎた。
彼女は、まずヤシンにだけ真相を打ち明けた。ヤシンは、自身の権力を使ってレヨンの関わりを隠匿した形で原因を特定し、幹部たちに対策を図った。
しかし〈限終〉の行動は素早く、あっという間に人類は追い詰められ、政権も瓦解した。こうなっては、レヨンの責任の隠蔽など何の意味もない。もっと広く原因を公開して対策をとっていればと悔やんでも後の祭りだった。
文明社会は全地球的に壊滅し、現在の地上に、まとまった政権を持った国家は存在しない。地球上全て合わせても数千程度の小さな都市国家が、細々と命脈を繋いでいる状態だった。今日も〈限終〉からの攻撃は止むことはなく、そう遠くないうちに人類は滅ぼされるだろうと、生き残った人びとのほとんどは諦めていた。
それでも、レヨンとヤシンはあらゆる手を尽くして〈限終〉に対抗してきたが、十年前にレヨンは病に倒れ、将来行うべき作戦要綱とタクラを残して息を引き取った。
そして今日が、レヨンが指定した、人類社会を取り戻す作戦の決行日だった。
「おまえがこの作戦の要だと、俺はレヨンから聞いてるんだ。頼むぜ」
「俺はそのために作られ、起動した。任せてくれ」
ヤシンは、AIによる擬似的な会話でも、それなりの信頼感を醸し出すものだと感心しながら、先を急いだ。それにしても、AIを倒すためにAIを搭載したアンドロイドに頼るとはなと思いながら。
二人はほどなく、ポイントに到達した。
「ヤシン、これから俺たちが突入する〈書店〉とは、いったいなんだ」
タクラがヤシンにそう聞いたのは、通路から縦坑を登り、今まさに〈書店〉近くのハッチに手をかけて開けようとした時だった。
「そういうことはインプットされていないのか」
「ああ。だが知っておいた方が、作戦に有用だと判断する」
「そういう感情みたいなものは、インプットされているのか」
「そのへんのバランスを取ったのはレヨンだし、俺には彼女の計画の詳細は不明だ」
「レヨンのことだから、理由あってのことだろうが、人類の命運や命を賭けるのに、なぜそんな曖昧さを残したのかな。まあいい。検証の時間もないし、信じるしかないな」
「その通りだ」
ヤシンは、ユニットの人工網膜に投影された時刻を確認した。用心して十分前に到着しているから、タクラの問いに対して簡単な説明をしてやる時間はある。彼は、強化し尽くして常人の倍以上の太さのある両腕を、ハッチのハンドルから下ろした。そして彼の足の下でタラップを掴み、見上げているタクラに言った。
「しかしまあ、そうだな。俺とレヨンの罪について話してやるよ。そしてそれに始末を付ける作戦がなぜ今日なのか、なぜ俺とお前なのか、〈書店〉とはなんなのかを」
ヤシンは話し始めた。
ヤシンとタクラが、〈書店〉近くの縦坑のハッチの下で作戦開始のために待機している二一二四年。そこから七十年を遡った、二〇五四年の夏——。
その年、ヤシンは首都にある国立大学工学部の電子工学科の三回生で、レヨンは機械工学科の四回生だった。にもかかわらず、というよりもだからなのか、二人ともレトロなアナログの機械などが好きで、ヤシンは大学からほど近い古書店街で古い図面を漁るのが、レヨンはその隣町の、楽器店などが集まるエリアで昔のアナログレコードを集めるのが趣味だった。
そんな二人なので、電子書籍より紙の本を好んだ。学科のテキストは電子データが主となって久しいが、趣味の本などはほとんど紙で買っていた。世の中はすでに電子書籍が大半で、紙の本は高価な贅沢品だったが、小まめに古書店を回って手に入れていた。
二人は、少しアナクロでアナログな趣味人が集まる〈懐古縁〉というサークルで出会った。名前の通り、懐古趣味の活動をしていた地味な学生サークルが、なぜ国家の実権を握るまでになったのか、現在では知る者もいない。当時のいきさつを知る人間は残っていない。いたとしても、小さな集落や、せいぜい数万人の都市国家しか存在せず、それらの連絡が途絶えた状況では、彼らが邂逅することはほとんど不可能なので、伝承されない。そうなったことへの引き鉄を引いたのは、間違いなく、〈懐古縁〉のメンバーたちだった。
始まりは、「紙の本を見直そう」というイベントを主催したことだった。大学近くの公民館での、ほんの内輪の集まりのはずだった。一日限りの催しで、五十人も来場すれば上出来というのが、ヤシンたちの予想だった。
だがイベントの数週間前から、SNSで拡散した情報は、どこでどう曲解されたのか反デジタルのイベントであるかのように伝わり、曲解したうちの一人が告知ページをプリントして大学で配布し、それが他大学にも伝わり、その波は学生以外にまで広がっていった。学生によるマイナーなイベントは、通常ならあり得ない、事前の盛り上がりを見せた。
「いやそんなこと絶対に、ぜーったいにあり得ないから」
これまでも集客に苦労し、閑古鳥の鳴くイベントばかり主催してきた、サークルの部長は信じようとしなかった。それはヤシンやレヨンも同じで、友人たちによるイベントの盛況の予想を聞いても、笑って相手にしなかった。
だが当日。次から次へと押し寄せる来場者に、サークルのメンバーたちは顔を見合わせた。
「なにが起きた」
「誰かにハメめられてね?」
「ほら、あれだよ、フラッシュなんとかいうパフォーマンス。今に皆んなで、踊り出すかなにかするんだ」
どれも違っていて、冷やかしはほとんどいなかった。その日を境に彼らは、反デジタルの旗手となった。
サークルのメンバー数は、イベントが終わるまでに八倍になり、怖じ気づいた部長が逃げるように脱退した。代わりに、体格が良く落ち着いていて、そのうえ人望もあり、学生らしからぬ押し出しの良さまであったヤシンが、祭り上げられた。レヨンは、彼を傍らで助けながら、いつも少し悲しげな、心配そうな瞳でヤシンのことを見ていた。
レヨンの心配は、あっという間に現実となった。メンバーは僅か一ヶ月で二千人を超えた。ほとんどが学外からの参加で、社会人も多かった。ヤシンは、やむを得ずサークルの組織を強化した。組織の再編成には、拙い学生の知識に社会人のアドバイスが加わったが、皆若く、理想ばかり高く、現場担当の裁量が異様に大きなものとなった。
とくに、首都圏支部長である女性メンバーのイルは、リーダーとして積極的に組織拡大を図り、勢力を伸ばしていた。
「これ、私たちがやりたかったことじゃないよね」
その間、レヨンはヤシンの側で、ずっとそう言った。ヤシンは頷いたが、すでに抜き差しならない立場になっていた。二人がとりわけ悩んだのは、きっかけとなったイベントのテーマが拡大解釈され、電子書籍が目の敵にされたことだ。二人とも、そんなことは望んでいなかった。
だが当時の社会状況の不安定さから、その不満をすくい上げるようにしてサークルは肥大し続け、やがて政治性を帯び始めた。さらに世界的には、国際紛争や局地的戦争が頻発し、ついに彼らの住む国も、防衛出動を拡大解釈したような軍事行動を国境を越えて展開し、国内外は混乱を極めていった。
二年の間にサークルは〈大回帰党〉と改称され、数年後には、全国どころか世界中に支部ができた。急進的で急激に膨張した組織らしく、権力を掌握したのは「フレキシブルな活動が可能な、裁量の大きな現場担当」たちだった。
その日、首都圏支部長のリーダーのイルが、精鋭二百人を率いて国会に突入した。運の悪いことに、この日の警備の半数近くが大回帰党の密かなシンパだった。さらに間の悪いことに、突入の二分後に首都が空襲された。被害は軽微だったが、国防軍はまずそちらに手を取られた。他にもあらゆる偶然が大回帰党に都合良く流れ、クーデターは成功してしまった。当初、どうせ中までは入れないだろうから、せいぜい派手に暴れて逮捕され、連行されるときにカメラにアピールしようと目論んでいたイルは、占拠した国会の議長席で、半ば呆然としていた。
同時に、世界各地の構成員らが一斉に蜂起し、ほとんど全て成功した。大回帰党に都合の良い偶然が各地で頻発したが、その下地にあったのは、デジタル社会の恩恵を受けている人々の中にさえ、デジタルへの根拠のない忌避感が深層意識に潜んでいた人間が多かったことが、大きく作用した。
ヤシンやレヨンたちは、次々に入る蜂起成功という現実感のない報告に、首を傾げ続けた。
「レヨン先輩、俺たちはなんで、こんなところに並んで立ってるんですかね」
二人は、石造りの神殿をイメージして作られたステージに、仲間たちと一緒に立っていた。眼下の巨大な広場では、百万人以上が、熱狂して波打っている。
「さあ? でも、あんなにも電子的データに不信感を持っている人が多かったのは、意外だったなあ」
「いや、そうじゃないでしょ。それは違いますよ。結局は、事実上の世界大戦状態に、世界中の人間が嫌気をさしていたんじゃないですかね。ただのタイミングだったんだと思いますよ、俺は」
「そう言われれば、そうかもねえ」
「レヨンはのんびりした口調だったけどな、心中穏やかじゃ無かったはずだ」
ヤシンは、狭い縦坑でタラップを握りしめ、彼の両足の間から頭を出して黙って聞いてるタクラを見た。
「あとは独裁政権お決まりの粛正だ。独創性の欠片もない」
「どんな人たちを粛正したんだ」
「知識層だ。その次は内部での粛正合戦で、疑心暗鬼の暗殺の嵐だよ。その結果が、今の世界ってことだ。人間だけじゃなく、記録も本もデータも破棄された。今じゃもう、どこかで原発がメルトダウンしても止める術はない。災害に襲われたら逃げて、逃げ切れなかったら諦めて死ぬ。精密な医療機器の開発や製造はもちろん、メンテナンスをできる人間もほとんどいない」
「少なくなったといっても、まだ人間は二億人近くいるのに」
「俺たちが権力を持ってから一定期間、知識を持つことは死に直結していた。知識が忌避される時代がひと世代以上続いた。もちろん、命がけで知識を吸収し、隠れて色々な研究をしていた人間もいた。だが連携も連絡もなく孤立していたから、大きな成果を上げることは難しかった」
「なんで知識層を殺した」
「独裁政権の定番だ。知識層は少ない方が、大衆は御しやすい。そして、こういうことはいったん始めたら、必ず暴走する」
「誰も止めなかったのか」
「まともな奴から消えていった。今日の作戦に直接繋がるのは、ここから先の話だ」
大回帰党が主要な国の政権を掌握して八年後の、二〇七二年。
最も先鋭的で精力的に活動し、粛正数もトップのイルが、密かな裏切りを行っていた。それは党というより、人類への裏切りだった。
「いつからだ」
ヤシンが、レヨンに問いかける。
「一ヶ月くらい前から。彼女の居所は分からない。人類の全てを破壊せよという命令を管理AI〈限終〉に組み込んで実行して、それをプロテクトして、それであの子は、どこかへ消えてしまった。もちろん、一人では無理だった。あの子の腹心が何人か、同じ時に姿を消しているの。もっとも、末端の子たちは、自分たちは微調整をしていただけと信じているみたい」
「イルは、革命の一番の功労者じゃないか。それがなぜ」
「彼女は、先鋭的過ぎて、突き抜けてしまったんだと思う」
「意味が分からねえよ!」
幹部の中にも、イルが〈限終〉に施したプロテクトを解除できる者はいなかった。〈限終〉は、党本部地下にコアを置き、全世界を繋いだネットワークで政権に係わるあらゆることを管理しているほか、インフラから防衛まであらゆることが集約されていた。
一点集約型のシステムは一度崩壊すれば、全てに波及する。その危険性を、イルは巧みに隠し通してきた。だがもともとデジタル機器を使えてもブラックボックスだった人間しかいない政権内部には、それを見抜ける知識を持つ持つ者は皆無だったので、状況は静かに進行し、人類への叛逆の日を迎えたのだった。
人類へ叛逆した〈限終〉は、インフラから軍事まであらゆる拠点に攻撃を仕掛け、あらゆる場所にアンドロイドやドローンなどの戦闘マシーンを送り込み、人類を掃討した。知識も知恵も失った人類にまともな対抗策は無く、瞬く間に滅亡の一歩手前まで追い詰められた。いまや党本部地下は厳重に防御され、誰も近づけない。
管理AI〈限終〉の叛逆から三年後の、二〇七五年。
都心から数キロの廃工場で会議が開かれていた。ここがこの時代の、事実上の世界の中心だった。
都心に建つ元の党本部は、管理AIの操る戦闘マシーンに囲まれて、近づくことはできない。
仮党本部になっている廃工場は、大きめの体育館ほどの広さがあった。機械類が撤去され、がらんとした空間の中央に、古びたスチールデスクをいくつか繋げたものが置いてある。そこに、八人の男女が座っていた。いずれも三十代から、最年長でも五十代前半だった。
二枚の鉄扉が軋んだ音を立ててスライドし、ヤシンが入って来た。三十代半ばになった彼は、スーツの胸がはち切れんばかりだった。ゆっくりとテーブルに歩み寄る。席に着いている八人が、目で追う。
ヤシンが、入口近くの席に着いた。彼はこの会議を招集した、現政権トップだった。
ヤシンの対面に座る、四十歳くらいの女が報告する。
「衛星は、今朝八時十一分十三秒に、打ち上げられました。現在まで、異常はありません。地球周回軌道へ向けて、順調に飛翔中です」
一同が頷いた。〈限終〉によって、世界各地の宇宙基地は軒並み破壊されていたから、打ち上げ施設として、首都郊外に建つ、高さ千メートルの電波塔を改造した。たちまち察知した〈限終〉の攻勢に、防衛隊は現有戦力の半分以上を割いて、打ち上げまでの数ヶ月間これを死守し、全滅した。
「状況は厳しいが、これで希望は残された」
ヤシンが言う。
「はい、この衛星には、数百万冊分のテキストデータが記録されたシリコンが搭載されています。一定の条件が整うまでは完全なスタンドアローンで、いかなる相手とのデータの送受信も行いません。地上の管制からも完全に切り離され、接続プロトコルはデータとしても物理的にも破棄されました。〈限終〉といえども、これをハッキングすることは、まず不可能です」
報告した女が捕捉した。
女から一人置いた、三十歳手前くらいの、一番若い男が言う。
「希望ってなんです? 今の話に、そんなものがあるようには聞こえなかったですが」
「すまないが、それは言えん。僅かでも〈限終〉に漏れたら、最後の希望は潰える」
ヤシンが答える。
「分からなくはないですが、その秘密主義が、現状を招いたのでは」
「だが、これが最善だ。信じてもらうしかない」
若い男は、不満そうに口を閉じた。
首都陥落は時間の問題で、行き着く先は組織的抵抗の終焉と、人類の遠からぬ滅亡だった。
「次に、〈書店〉についてです。むしろこれが、衛星打ち上げの動機と言えます」
女が、次の議題に移る。
数年前から〈限終〉は、廃墟となった都市の中に〈書店〉を作り始めた。
それは、一つの都市に一店舗ずつ作られた。住人がほぼいなくなった廃墟の中。そこにある日、〈限終〉に作られ、制御された自動建設機械が集まってくる。彼らは、ものの数日でそれを建ててしまう。
往年の都市文明から切り取ってきて置いたような新築店舗が、廃墟に建つ。外観は一つ一つ違うが、店の外には電飾看板が掲げられ、店内も明るい。どん底のエネルギー事情にある人間からすれば、腹立たしい光景だ。
店内では人間型アンドロイドが、あたかも店員のように歩き回っているが、客がいるわけでもなく、何をしているのか不明だった。彼らは、ご丁寧にも書店員がするようなエプロンまで着けていた。
書棚らしきものも見えるが、実際に本が並んでいるのか、ダミーなのか、それとも別の何かを陳列しているのか分からなかった。探ろうにも、店の外には三十センチメートルほどの金属球体が、百機以上もうごめいている。このセキュリティボット、通称〈ボール〉は、必要に応じて伸縮する三メートル以上の自在アームが数十本も仕込まれ、さらに高出力レーザーを備える。上空には、全長前翼それぞれ一メートルほどの自立警戒ドローン、〈グリーンバット〉が数機、常に飛び交い、近づくものには内蔵の機関砲を浴びせかけていた。
〈限終〉の狙いは不明だった。なぜ、わざわざ標的になるような施設をあちこちに建設するのか。誘っているようにも見えた。
「店には、必ず〈限終〉の解除キーがある。〈書店〉建設は、イルに仕組まれたプログラムだ。人一倍、物理書籍にこだわりのあった奴だ、こんな目立つものを意味なく作るとは思えない。確認のしようはないが、俺は確信してる。〈限終〉は、自分を破壊する物理システムを自己生成している。そこに〈限終〉の判断や計算はない」
「わたしも、そう思う。イルは必ず、そういった意図的なセキュリティホールを作っているはず」
「結局イルは、暴走させてはみたが、止める方法も組み込んでおかないと不安だったということだな。これまでに何十億人殺したと思ってんだ」
「それはそうだけど、今は彼女の不安定な性質に期待するしかない。それに、極小の偵察ボットや超望遠での撮影、色々な波長でのスキャン、ほかのあらゆる観測によって、私たちの憶測以上の高確率で、あそこには解除キーの起動システムがあると判断できる。そして〈限終〉の攻撃命令が止まれば、あそこは、失われた人類の叡智の宝庫になるの」
「文明を再興できるか」
「そうなるはず」
「おもちゃ箱を引っ繰り返して、次はお片付けの時間です、か。ふざけんな」
「でも私たちは、それをしなければ」
「分かってるよ……。それも、イルの人間性なんていう、あやふやなものに賭けてな……」
——現在。
ヤシンは語り終えた。
「それから俺たちは、あらゆる手を使って〈書店〉へ潜入しようとしたが、死人が増えるだけだった。
やがて防衛隊も中枢メンバーも、次々に倒れていった。歳を取って身体がきかなくなって一線を引く奴も増え、一部は俺のように仮体ユニットを増設、交換しながら戦ったが、限度がある。レヨンが倒れて、実行部隊は、今は俺一人だ」
「でも、俺が起動した」
「そうだ。お前は絶対にハッキングされちゃいけなかったから、どこともリンクしてなくて、ごく単純に、タイマーで目覚めた。ただ起動には、俺か、俺の意を受けた者の認証が必要だった。たまたま俺はまだ生きていたんで、自分で認証して起動させ、ここへ連れてきた訳だ」
ヤシンは、縦坑の足もとにいるタクラを指さした。
「レヨンはなぜ、解除キーである俺を、人間型に作ったんだ」
「それは、〈書店〉の中に入ってみれば分かる。さあ、行くぞ!」
〈書店〉近くの、大きな瓦礫の陰に隠れた細かい瓦礫が盛り上がるように膨らみ、崩れた。縦坑のハッチが大きく開くと同時にヤシンが飛び出し、素早く大きな瓦礫の陰に身を寄せる。続けてタクラがするりと抜け出て、別の瓦礫に身を潜める。
陽はとうに落ち、〈書店〉の店内照明や屋外看板の電飾が届く範囲だけが、夜を遠ざけている。この〈書店〉は、三階建てでワンフロアもかなり広かった。各階に百人近い人間が入れるだろう。
この廃墟の街には、まだ二、三千人は暮らしているはずだが、ボットやドローンから隠れ、〈書店〉には近寄らないので、あたりはひっそりと静まりかえっている。
「おまえは向こうへ」
ヤシンがタクラに、〈書店〉側面に回り込むよう指示する。彼を先行させるのは、人間を超えた俊敏な動きでセキュリティボットらをかいくぐれることもあるが、体温その他の諸相が人間とは違うので、センサーに引っかからないということが大きかった。
「よし」
ヤシンも飛び出した。こちらは〈書店〉の正面へ出る。陽動だ。
彼も仮体の強化ユニットで、常人を遥かに超える運動能力を発揮できる。タクラにハンドサインを送りながら駆け抜ける。ボールやグリーンバットにに傍受されるので、通信は使わない。
今夜、この時間にこの上空を、彼らが五十年前に打ち上げた衛星が通過する。レヨンの作戦が今夜を選んだのは、このためだ。タクラのタイマーも、それに合わせてセットされていた。
ボールがヤシンを囲み、グリーンバットが彼に照準を合わせる。
タクラが側面からニードルガンを乱射しながら飛び出し、ジグザグに走りながら〈書店〉正面中央の、分厚いガラス製の自動ドアに迫る。もっとも、このドアが自動で人間を招き入れたことはない。
「来た!」
衛星が、約三百キロの真上にさしかかった。肉眼では勿論、彼らの装備で確認できるものは何も無い。ヤシンは、レヨンの計算を信じ切っていた。レヨンが言ったのだから、この瞬間、上空に衛星はいるのだ。彼にとって、それは揺るがない事実だった。それに——。
「すぐに、本当かどうか分かる」
片腕でボールとグリーンバットをなぎ倒し、もう片方の手に持った銃で撃ち落としながら、タクラが自動ドアに取り付いた。
ドアが、開いた。
その瞬間、ボールも、グリーンバットも、動きを止めた。
店内から、ゆったりとした足どりで人間型アンドロイドの店員が歩み出た。
「いらっしゃいませ、お客様。何かお探しの本が、ございますでしょうか」
「解除キーを」
静止したボールに囲まれたヤシンが見つめる先で、タクラが言った。
「かしこまりました」
アンドロイドの店員が答える。
ヤシンが、ほっと息をついた。
タクラは、これまで誰も入ったことのない店内に静かに入り、溶けるように四散した。
亡くなる直前、レヨンは衛星の軌道計算と共に、タクラを人型にした理由をヤシンだけに伝えていた。
「人型に作られた解除キーの起動アイテムであるタクラは、でも人間じゃない。彼には、ボットもアンドロイドの店員も人間にするようには対応できない。彼は、その姿で相手を混乱させ、引き起こしたバグで、彼らの懐に入って解除キーを起動できる。バグで稼げるのは一秒。その一秒を、タクラに託したの」
今、〈書店〉の中には、衛星からの膨大なデータが流し込まれ、管理AIは処理落ち寸前だった。そして再起動したとき、人類に敵対的なプログラムは消去されていた。
「俺たちの勝ちだぜ、レヨン先輩。イルは、やっぱりイルだったよ」
世界各地の〈書店〉で、管理AIの対人類基地周辺で、あらゆる場所で、ボールやグリーンバットは活動停止、二度と動くことはなかった。
ヤシンは、機能が停止したため開いたままになっているドアに近づいた。店内に入る。タクラはアンドロイドだから、入店した人間は、彼が初めてだった。
あちこちに停止したアンドロイド店員が倒れている。棚には、紙の本が並んでいた。本物ではない。3Dプリンターで出力した、一種の復刻版だ。
欲しいものは、すぐ見つかった。イルが指示し、レヨンが介入したプログラムだから、当然と言えば当然だった。
ヤシンはそれを手に、床に腰を下ろした。膝の上に広げたのは、古い時代に描かれた機械図面の図面集だ。
〈書店〉のセキュリティが機能停止したことで、何か目ぼしいものはないかと、生き残りの住人たちが恐る恐る近づいて来るのが見える。いずれ彼らの中から、この膨大な知識を活かして文明を再興する者が出るだろう。
「だけど、それは俺じゃない。身体は取り替えがきいても、脳だけは自前だ。百二十歳を過ぎて、耐用年数はとっくに終わってる。そろそろそっちへ行くよ、レヨン先輩」
ヤシンの手から、図面集が落ちた。
その日は、彼らが百年前に、公民館でイベントを開いた日だった。テーマは、「紙の本も大切に」だ。
(イラスト:大谷津竜介)